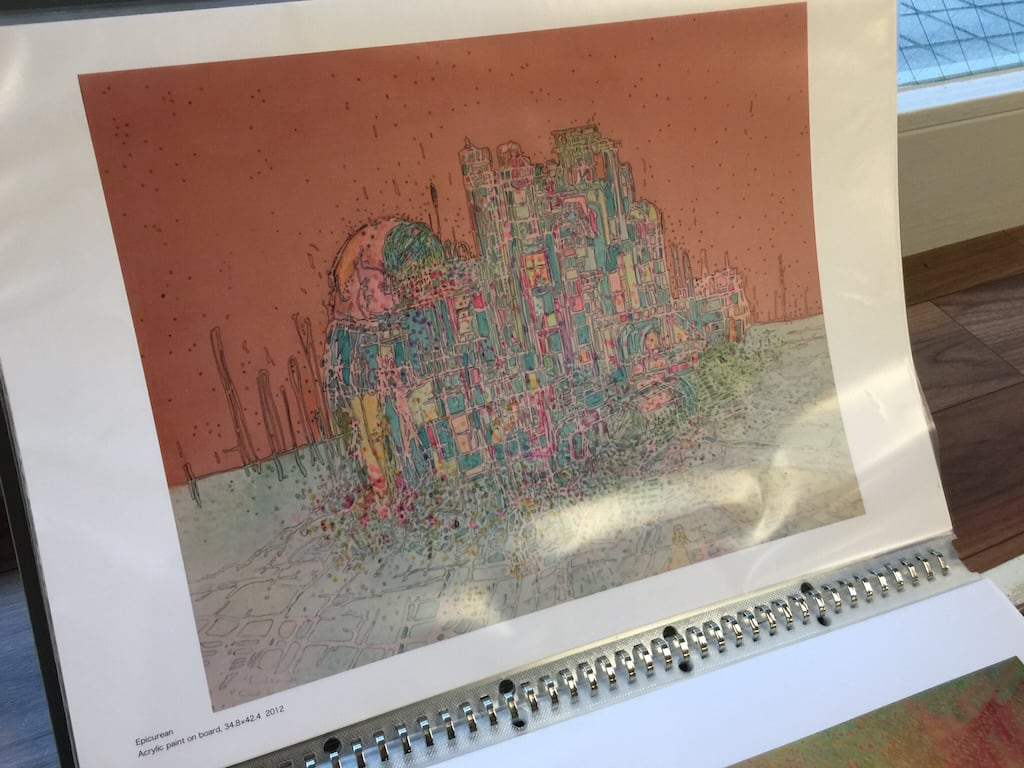時をさかのぼる小説で文明を脱ぎ捨ててしまえ。カルペンティエル「失われた足跡」(岩波文庫) [#003]
よく小説は時も場所も飛び越えるといいますが、それはたいてい、書かれた時代と場所が違うことを指しています。しかし読み進めるほどに時代がさかのぼり、心が暑苦しく厚着していた文明の虚飾をはぎ取られてゆく読書体験はめったにできるものではありません。
スイス生まれでキューバ育ちの小説家、アレホ・カルペンティエルの「失われた足跡」はまさにそうした、文体の魔術によって読んでいるこちらの精神が変わってゆく小説です。
さかのぼる時間と変化する心象風景
作曲への情熱を失った主人公の「私」は大都会で退廃的な日々を過ごしていますが、博物館の依頼で南米の奥地に幻の原始楽器を探す旅にでます。
ラテンアメリカの首都のとある首都で騒乱に巻き込まれ、バスの旅と船の旅で大河をさかのぼり、原始的なインディオの村、ジャングルのなかに新たに創建されたエデンのようなサンタ・モニカ・ロス・ベナードスの街へと進むうちに登場するのは、かつての征服者時代のなごりのような宣教師、オデュッセイアーを大事に抱えて金山の夢をみるギリシャ人、常に都会の虚飾を思い起こさせる占星術師である「私」の愛人、自然を体現した肉感的な女ロサリオなどのサーカスのような顔ぶれ。
当初は建築を志し、音楽の造詣も深かったというカルペンティエルの文体は最初は衒学的で、隠喩や象徴に満ちています。このあたりは読んでも頭に入らないほどだったりするのですが、この過剰さこそが演出の目的だということを意識して読み進めてゆくとそのうち変化がやってきます。
南米の首都での動乱の描写で暴力的な楔が打ち込まれ、銃弾一つで人生が絶たれてしまうリアルさが退廃的な雰囲気に目覚めをもたらします。
そこからは南米の絶景や、大河の神秘、インディオたちの素朴な生活が描かれるたびに使われる用語や比喩が直接的で感覚に訴えるものに変化してゆく奔流に流されてゆくのでいいでしょう。
単に未開の地にやってきたという描写にとどまらない、筋が進むほどに時がさかのぼって原始時代に戻ったかのような感覚が襲い、主人公である「私」の内面もまた文明人のそこから裸で大地を踏みしめることに違和感を覚えない始まりの人のそれへと回帰していきます。
しかし小説はそこまで楽天的に明るく終わることが許されません。新しい愛を、新しい音楽を見出したそのときに、「私」を待っているのは破局そのものなのです。
革命運動に加わったためにパリに亡命し、そこで代表的なシュルレアリストらと交流したカルペンティエルは、旅を続ける漂泊の人生を送った一方で、常に南米に自分自身のルーツを探し求めた作家でした。
カルペンティエルは魔術的リアリズムの源泉といわれますが、自身の故郷へと帰ろうとする思い、自分の本源を探そうとする想いが、ラテンアメリカという舞台と結実することで現実を超越するような文体を生み出せたのでしょう。
ラテンアメリカという個別の地域を描いているのに、文明と自らを切り解けないすべての人間に普遍的なテーマを描くことに成功している、稀な作品だといえます。
まだ一度しか通読できていないので深く読みこなせていないのですが、この見いだしたと思った時にはすでに見失っている「本来の自分」を探しに、なんとなく手にとってページをめくってしまう一冊です。
 失われた足跡 (岩波文庫)posted with amazlet at 15.09.02カルペンティエル
失われた足跡 (岩波文庫)posted with amazlet at 15.09.02カルペンティエル
岩波書店
売り上げランキング: 41,680
Amazon.co.jpで詳細を見る