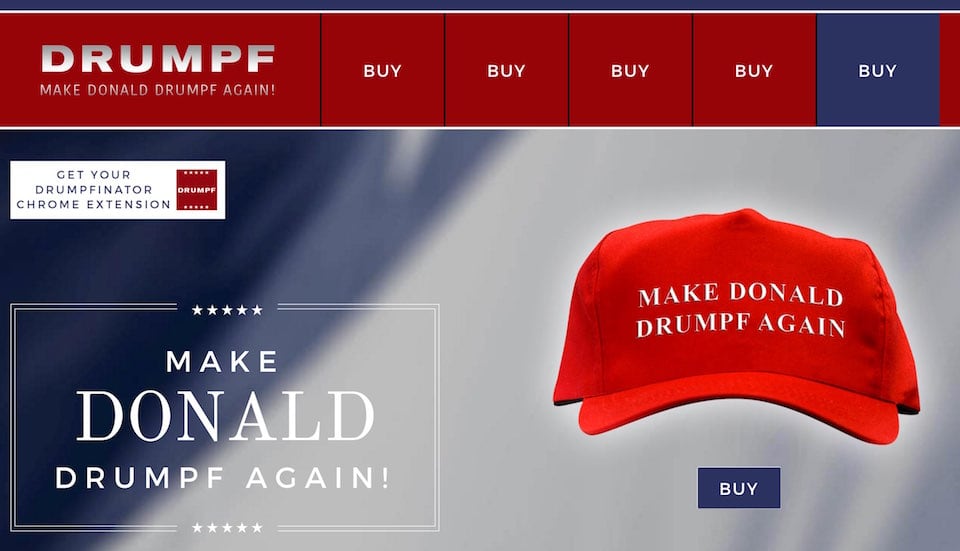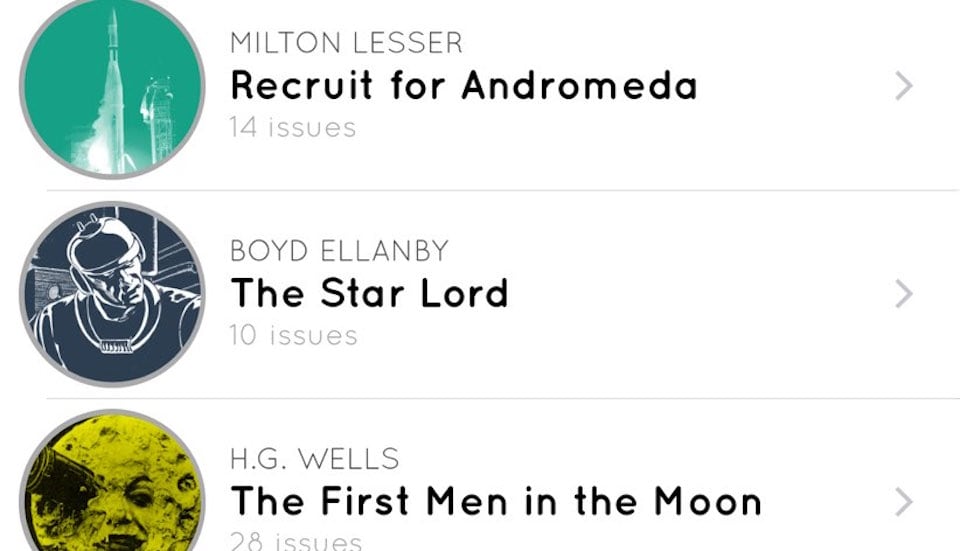邦訳と英訳との2重の読みから、自分だけの作品世界を体験する
読書は、読んでいるテクストに対して心を開き、書き手の意図を汲み取りつつも豊かな解釈に開かれた、自分だけの「読み」を楽しむところに深い喜びがあります。しかしそのテクストが信頼おけない際、私たちはなにを読んでいるのか焦点を合わせることができない危機に陥ります。
海外文学を読んでいるとよくそうした瞬間があり、先日も一例に出会ったので紹介したいと思います。先日他界したウンベルト・エーコの小説、「フーコーの振り子」の77章の末尾を読んでいたときのことです。
これが日本語訳では以下のようになっています。
なのに、僕たち三人は、まるで連中をあざ笑うかのように、彼らと鬼ごっこを楽しもうとしていたのだ。そんなに世界制覇の陰謀が欲しいのか、いいだろう、みせてやろう、僕達が作ったのは世界に二つとない最高の陰謀なんだから、さあ、鬼さんこちら、手の鳴る方へ。
ざまあみろ! ― 二日前の夜、私は自分にそう言って聞かせていた ― お前がここにいるのは、あのフーコーの振り子の下で何が起こるかを見届けるためなんだろ?まことに暗がりに鬼つなぐとは今宵なるべし、まあ、楽しみに待ってるんだな。
3人の主人公がテンプル騎士団の「計画」をでっちあげて遊んでいるうちに、虚構が現実に追いついてしまっている様子を描き出していますが、邦訳をされた藤村昌昭先生の訳文は、ひょうきんで、ところどころに原文を越えた書き込みが目立ちます。「まことに暗がりに鬼つなぐとは今宵なるべし」など、井原西鶴「世間胸算用」からの引用です。
失礼ながら日本語の訳文はこうして跳ねまわる側面があって時としてわかりにくいなあと思っていたのですが、同様の場所を英訳本で読むとまったく違う雰囲気を感じ取れます。
But no. We, the sardonic, insisted on playing games with the Diabolicals, on showing them that if there had to be a cosmic plot, we could invent the most cosmic of all.
Serves you right, I said to myself that other evening. Now here you are, waiting for what will happen under Foucault’s Pendulum.
もちろん「まこと暗がり〜」の表現はなく、「鬼さんこちら」に対応する部分もありません。
また、雰囲気も気になります。「ざまあみろ!」と自虐的に自分にむけて独白している主人公を描き出している邦訳に対して、英訳は “Serves you right” と「身から出た錆」「自業自得」という諦観を前に出した翻訳をしています。
「フーコーの振り子」が英語だと最後になっていて、文学的効果をもたらしているのも、邦訳とは違います。試しにこの部分の私訳を試みると:
しかしやんぬるかな、冷笑をうかべた私たちはこの悪魔たちとの遊戯にこだわり続けてしまった。宇宙的な陰謀があるとあくまで言い張るなら、私たちが最高の陰謀を発明してみせつけてやると。
身から出た錆だと、私はあの夜、自分に言い聞かせた。そしてこのありさまだ。あのフーコーの振り子の下で何が起こるのか、おののきながら待つはめになっている。
このような感じでしょうか。イタリア語版の「フーコーの振り子」は手元にありませんでしたし、あったとしても私のイタリア語では果たして投げやりな雰囲気なのか、諦めの雰囲気でかかれているのかもわからないでしょう。
英訳が正しいとするならば、主人公のカゾボンはこのシーンでは自分がどんなパンドラの匣を開けてしまったのか自分でもわからずに、むしろ恐怖を感じながらうずくまっていたはずです。
作品は、どこにある
難しい本を読む際によくあるのですが、こうして訳文自体が信頼おけない、あるいは過剰に訳してしまっている場合、作品との向き合いは困難で、独特の面白さをもちはじめます。
邦訳は邦訳で一つの作品として扱うことができます。そこにイタリア語の原文の雰囲気を探し求めて英訳との比較も加え始めると、真のテクストがどこか宙に浮いた状態で、私の解釈した脳内の「フーコーの振り子」が誕生します。でもこれが作者の意図だと保証するものはありません。エーコですから、そもそもそんなものは読者にむけて放り出しているのかもしれません。
この危機を楽しみ、こうした重複的な読みをすることで、「真のテクストの不在」(それは単にイタリア語が読めないということですが)をいいことに自分だけの読みが開かれる。これも翻訳ならではの楽しみです。
あまりに時間がかかるので気になった部分を詳細に検討したい時にしかできないのですが、エーコのような一筋縄ではいかない著者の場合には、こうした探索は楽しい推理のひとときになるのです。
(補記)
写真は、パリ工芸院に設置されている実際のフーコーの振り子の先端です。これについても、また日を改めて。