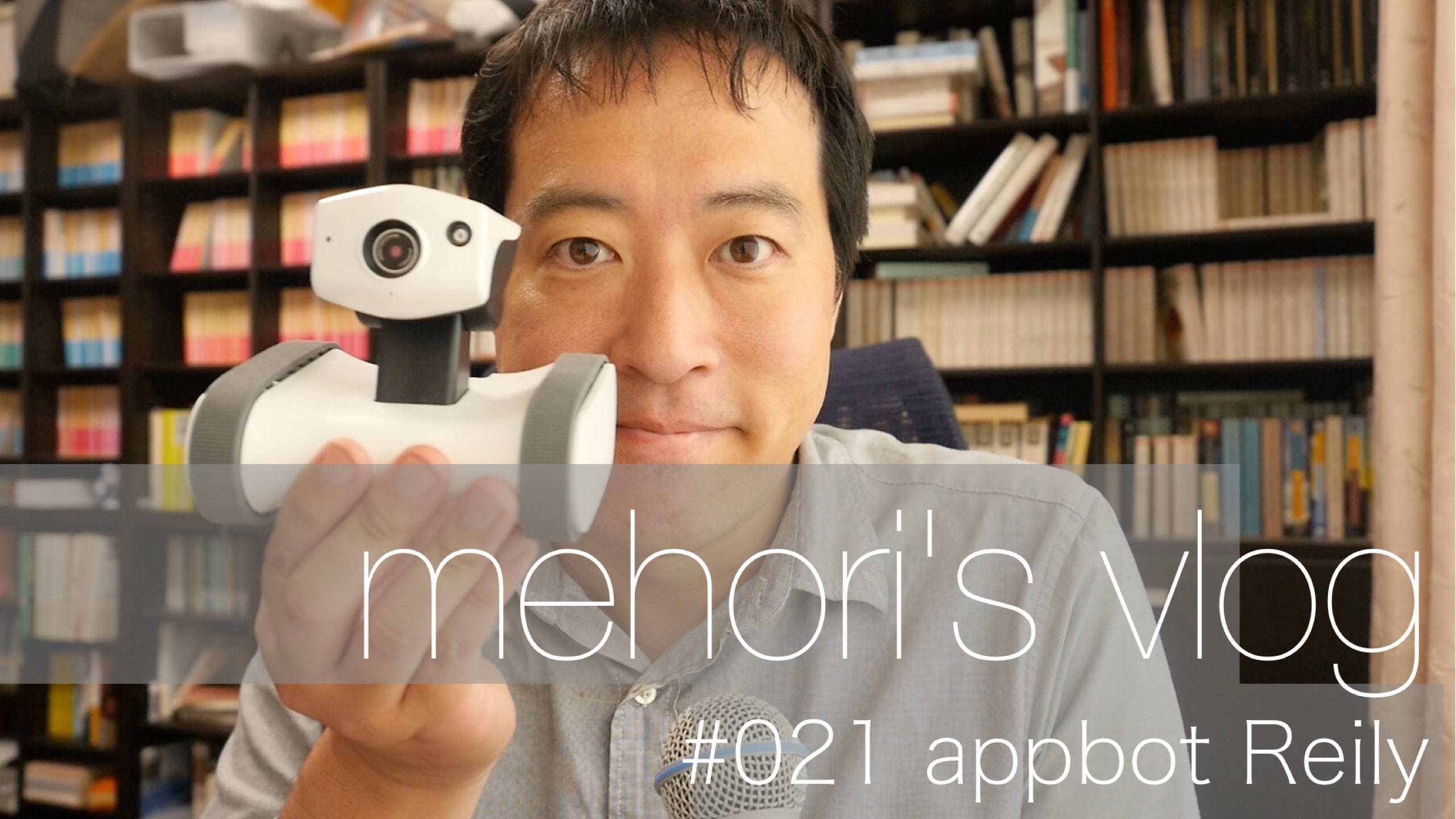ロボットらしさとは、人間らしさとは、を "Alter" に学ぶ
文化庁メディア芸術祭の受賞作のなかでも、ひときわ異様な雰囲気を放っているのが大阪大学・石黒研究室と、東京大学・池上研究室の共同で制作された “Alter” です。
芸術には動かない彫刻もあればすでにみた “Interface I"のような動きを取り入れたものもあります。最近は人間自身を作品に取り込むものもあり、動くのか動かないのか、生きているかいないかといった差異は、すでに制作上の制限としても、解釈の寄って立つ場所としても乗り越えられているといっていいわけです。
そんななか、この “Alter” は現代的な彫刻であり、ロボットであり、機能をもった人形であり、動きをもった生命の模倣であり、それでいてそこにはやはり人間はいないといった多義性をもって鑑賞者を揺さぶります。
「こいつ…動くぞ」どころではありません。「お前…いったい何者なんだ」と問いかけたくなるのですが、その答えがそっくりそのままこちらに返ってくる。そんな作品なのです。

“Alter” 自身は42本の空気圧アクチュエータで構成された、機械がむき出しになった胸と腕をもつロボットで、それが周囲に置かれた照度センサー、距離センサー、音センサーなどのインプットを受け取ります。
そして脊髄のそれを模した信号生成器とニューラルネットワークが、そうした周囲の環境にあわせて複雑な動きを作り出していきます。最初から人間らしい動きをさせようとしたのではなく、そうした数学的なモデルに環境データを入力するだけで、ある程度は生命のような動きを作り出すことができるという仕組みになっているわけです。
「あまり人が周囲にいては、センサーが壁のように認識してしまって、本来の動きが出せない」と制作者の方が言っていたのが印象に残って、なんとなく群衆が立ち去るまでその場所で待っていると、“Alter” はしだいに手足を無作為に振り回す惑乱した動きから、落ち着いた間欠的な動きへと変化してゆくのでした。
音楽をきかせれば、それにあわせて拍子を取ることもあるという “Alter” は、しかし私たちが想定している意味では「考える」ことも「認知」を行っているわけでもありません。
しかしそこに生命らしさを見てしまうのは、私たちの心の側にある何かが反応しているのか。それとも生命とは、他の生命からみたら本来このように不気味で理解不能なもので、“Alter” はそれ自身として自然なのか。
そんなことを考えさせられます。この作品の前に立つときには、本来は孤独を好む設計をされているのだということをどこかで思い出しながら、そっとセンサーの感知範囲を歩いてみてください。
第20回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展
-
会期:2017年9月16日(土)~9月28日(木)
-
NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]、東京オペラシティ アートギャラリー
-
入場料:無料
(本記事は文化庁メディア芸術祭の受賞作品展報道関係者向け内覧会に参加して取材をしています)